| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『ローマの休日』 |
|
|
| 『ローマの休日』 |
|---|
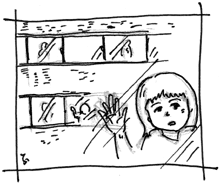 唯子の世界はいつもガラスの向こう側にあった。物心ついた頃から病院のベッドの上でガラス窓の向こうを眺めていた唯子は、春の桜も夏の入道雲も秋の落ち葉も、全部そこから見た。どうして自分が他のみんなのように学校にも行けず、ずっとここにいなければならないのかを知ったのは何年前だっただろう。骨髄性白血病って言ってね、と当時の担当医は言った。
唯子の世界はいつもガラスの向こう側にあった。物心ついた頃から病院のベッドの上でガラス窓の向こうを眺めていた唯子は、春の桜も夏の入道雲も秋の落ち葉も、全部そこから見た。どうして自分が他のみんなのように学校にも行けず、ずっとここにいなければならないのかを知ったのは何年前だっただろう。骨髄性白血病って言ってね、と当時の担当医は言った。「唯ちゃんの体に合う骨髄を移植すれば治るんだよ。今はその骨髄を待ってるところなんだよ」 そう言われてからもう三年以上が経つ。その間に唯子は14になっていた。 そんな唯子の楽しみは、病室に置かれた自分専用のテレビで映画を観ることだった。母親に頼んで借りてきてもらったビデオを、もうずいぶんたくさん観た。母親の趣味だったのか、オードリー・ヘップバーンのものが多かった。中でも唯子はローマの休日が好きだった。 お城を抜け出したアン王女がグレゴリー・ペック演じる新聞記者と出会ってべスパで街を走り回る。つかの間でも、そんなふうに自由を楽しむアン王女が羨ましかった。 一日だけでいい。自分もあんなふうに外に出て走り回ってみたい。あんなフレアスカートをはいて、アイスクリームを食べながら街を歩いてみたい。無理だろうけど、ジョーみたいな素敵な人と出会って、デートして…。 すると想像はどんどん膨らんだ。唯子は白い壁に囲まれた自分を、窮屈なお城で過ごすアン王女と重ねることで、退屈な病院での生活をほんの少しだけ紛らわせることができたのだった。 そんなある日、唯子は同じ入院患者の男の子と知り合いになった。病院の廊下を歩いていた唯子の脇を、ものすごい勢いで車椅子が通り抜けて行き、唯子の持っていた歯磨きセット入りのポーチが床に落ちた。彼は器用に車椅子を操って戻って来ると、ごめん…と唯子に謝った。それが将太だった。 将太は唯子より二つ年上の16歳で、笑うと片頬にえくぼのできる、やんちゃで、いつも看護婦さんに追い掛け回されているような人だった。 「俺はさぁ、骨髄ケガしちゃって今は車椅子。唯ちゃんは?」 「私はー…骨髄性の白血病って言って…自分に合う骨髄を待ってって言われてもう三年くらい経つのかなぁ…」 そんなふうに、同じ骨髄に障害を持つことからよく話をするようになった。将太は外科病棟に入院しているはずなのに、車椅子を全速で走らせてはよく唯子の病室に遊びに来た。そして後輪だけで走って見せたり、廊下の端から端まで何秒で走れるか…なんてむちゃくちゃなことをして唯子を驚かせる。そしてそのたびに看護婦さんに見つかっては、早く自分の病棟に帰りなさいと怒鳴られて逃げ回っていた。将太は自分のケガのことはあまり話さなかったけれど、バイクの免許を取ったばかりで交通事故に遭って入院しているということだけは判った。唯子は、将太もきっとケガをした自分の骨髄の『代わり』を待っているのだろうと思い、と同時にバイクの免許と聞いて途端に顔を輝かせたのだ。 「いいな、いいな。将太くんさ、べスパって知ってる?」 「知ってるよ。ローマの休日に出てきたやつだろ?」 そう将太が言ってくれたのも、自分の世界に新しい仲間ができたみたいで嬉しかった。だから唯子は「いつか元気になったらバイクの後ろに乗せてね」と無邪気にねだったのだ。すると将太は少しだけ困った顔をしてから、じゃあさ…と笑って唯子を中庭へ誘った。 「あの映画みたいに、二人でこっそり抜け出そうよ」 言われて、将太と顔を見合わせて頷いた。五月の天気のいい日の午後だった。 窓から見ているだけだった中庭に出ると、将太は「べスパの代わりな」と自分のひざを叩いて見せた。二人乗りしようよ。そう言って、唯子を乗せた将太が走り出す。中庭の小さな噴水の周りをぐるぐると回った。頬に当たる風が気持ち良くて、唯子ははしゃいで声を上げた。カーディガンを羽織っただけのパジャマ姿がちょっと残念だったけれど、そのうちそんなこと気にならなくなるくらい楽しかった。ちょっと疲れて階段に座っていると、将太が病院の自動販売機でアイスを買って来てくれた。ぜんぜんおしゃれじゃない、棒付きのアイスだったけれど、唯子はおいしいね、おいしいねと何度もくり返して食べた。 そしてまた将太の車椅子に二人乗りして、今度は表玄関の方へも行ってみた。そこで看護婦さんに見つかって、二人で逃げ回った。まるで映画の中のアン王女みたいだと、その時、唯子は必死に将太の肩にしがみついていた。 それからしばらくして、適合するドナーが見つかった唯子は手術を受けた。心配していた拒絶反応もなく退院の日を迎えた唯子は、その日、母親が迎えに来る前に「良くなったら本物のべスパね」と将太に言った。将太は笑って頷くと、唯子に向かって小さく手を振った。病院を出たタクシーの中で、あの子と何話してたの?と訊かれた唯子は「内緒」と肩をすくめてみせた。母親に、そんな小さな秘密を持つことさえ嬉しかった。すると隣に座っていた母親が言った。 「将太くんって言ったっけ。あの子、まだ16なのにこれからずっと車椅子なんて可哀想ね」 そこから先は、母親が何を言ったのか覚えていない。唯子は知らなかったのだ。骨髄損傷は『代わり』が見つかっても治らないということを。  その後、唯子は普通に学校へ行けるようになり、友達もできた。念願のフレアスカートを履いて、渋谷のスペイン坂へも行ってみた。ジェラートというイタリアから来たアイスクリームを片手に気取って階段を降りてみる。やっと夢が叶ったと思った。
その後、唯子は普通に学校へ行けるようになり、友達もできた。念願のフレアスカートを履いて、渋谷のスペイン坂へも行ってみた。ジェラートというイタリアから来たアイスクリームを片手に気取って階段を降りてみる。やっと夢が叶ったと思った。けれど唯子は、あの日将太と食べたアイスほどおいしいとは思わなかったのだ。 彼はどうしているのだろう。病院の玄関で別れたあの日から将太とは会っていない。 2003.4.30. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『ローマの休日』 |