| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『恋愛小説家』 |
|
|
| 『恋愛小説家』 |
|---|
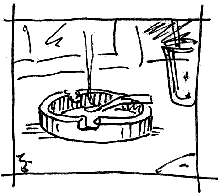 「私、描いてみる?」
「私、描いてみる?」早苗さんはそう言って顔を左に傾け、ふうっと煙を吐き出し、どう?という顔で僕を見た。 僕は慌てて視線をそらし、早苗さんの耳にかかった長いきれいな髪を見つめた。僕が、絵を描くのが趣味なんです、と言った後、彼女はそう言ったのだ。からかっているようには見えなかった。黙っていると、話は別の話題に移っていった。 僕らは歌舞伎町のマクドナルドの2階の、一番隅っこに向かい合って座っていた。 早苗さんはよくしゃべる人で、僕が黙っていても会話が続くのでありがたかった。僕はちらっと辺りを見た。マクドナルドの騒音の中で、こんなきれいな女性と一緒にいる自分、というのを考えてみた。どうだどうだ。僕は舞い上がりつつあった。 僕はあまり大学に行かなくなっていた。何か違う気がしながらも、目の前に並べられた進路の中から、[進みたい方面]を選び出し、受かったところに入学した。 大学の授業もつまらなくなり、同時に大学に関わる、人、もの、全てもつまらなく思えてきた。何かおもしろいことを大学以外に見いだそうとやっきになっていた。 僕は、パーティーの裏方、というボランティアみたいなものを始めた。交通費と食事は出るが、バイト料はない。たまたま見つけた映画雑誌の記事を見て電話したら、すぐに来て下さい、と言われた。主催は小さな配給会社で、パーティーもその読者の交流会のようなものだった。そこに行けばどうなる、というものでもなかったが、映画が好きな人がたくさん集まる場、というのが僕には魅力的だった。 新宿三丁目にあるベローチェに行くと、数日前に面接をした男性ディレクターが一人の女性と一緒に待っていた。細い人だな、と僕は思った。 「これから君と一緒にパーティーを盛り上げてもらうことになる、早苗さんだよ。君より、4つ上かな。」ディレクターは、ニコニコしながら言った。 「はじめまして、早苗です。」少し舌足らずな声で、彼女は頭をぺこりと下げた。長い髪が、すべるように前に垂れた。きれいな茶色だな、と思った。 マクドナルドを出る時、早苗さんが先に階段を降りた。後ろから、早苗さんの長い髪の毛が、階段を下りるのと同時にたん、たん、と揺れるのが見えた。 外は冷たい風が吹いていた。ありとあらゆる方向に、人々は行き交っている。僕らは並んで歩いた。終電大丈夫かなあ、と早苗さんは早足になった。僕は黙ってついて行きながら、大きなくしゃみをした。 早苗さんがこっちを見たので、ちょっと風邪気味なんです、と歩きながら僕は言った。 「駄目じゃないの、そんな時に出歩いちゃあ。」早苗さんはいきなり自分のマフラーをはずし、はい、これしてなさい、と僕に手渡した。断る暇もなかった。僕はそれを首に巻いた。ふわり、といい香りがした。 僕は、コトリ、と恋に落ちた。 早苗さんと僕は、それから週に2、3回は会うようになった。パーティーは毎月開かれ、その都度テーマを決めてその準備をしなければならない。でも僕らは、パーティーとは関係ない話をずっとしていた。いつもいつもドトールとかファースト・キッチンといったお店で、学生の身分の僕にはそれがありがたかった。 早苗さんはよくしゃべり、それを聞くのが僕は好きだった。ただ、話の端々に出てくる、画家の男、というのが気にいらなかった。 ある時、早苗さんに手紙を出そう、と急に思い立った。 早苗さんは新荻窪にある小さな出版社で、編集の仕事をしていた。そしていつも帰りが遅いようだった。何か素敵な言葉を書きたいな、と思った。 レンタルビデオで見た『恋愛小説家』のジャック・ニコルソンが言った台詞が頭に浮かんだ。 “君に会って…いい人になろうと思った。” この映画を早苗さんが知ってるかな、と一瞬思ったが、まあいいや、と思った。言葉尻を変えて、文章の中に引用した。 返事は驚くほどすぐに来た。僕は立ったまま4回、そしてしばらくして3回読んだ。幸い、『恋愛小説家』には触れられていなかった。“家に帰って来たら、君から手紙があったのでびっくりしました。”と手紙は始まっていた。“君はほんとに、私にとって大事な、大事なおとうとのような存在です。” ボランティアは、それからまもなく、やめた。パーティーはいろんな人が来てそのときどきは楽しかったが、それだけだった。何か、もっと後に残る事がしたかった。 その日は雨が降っていた。土曜のお昼だった。いつものように早苗さんのピッチに電話すると、彼女は泣いていたようだった。すぐに、画家の男、が頭に浮かんだ。 「すぐ行くから。行って笑わせるから。」僕は無理矢理決めて、電話を切った。 神保町にある早苗さんの部屋まで、ちょうど一時間だった。駅で降りて、しばらく歩く。少し前に、早苗さんが友人と自室で開いたパーティーに招かれて行ったことがあった。その時の記憶をたよりに、僕は急いだ。梅雨の中、僕の額からは、汗が吹き出していた。 ベルを鳴らすと、少し間があって、ドアの向こうから早苗さんの「はーい。」という声がした。 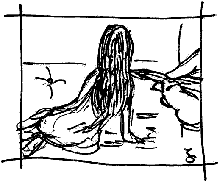 化粧が濃いな、と僕は思った。泣いていた顔を隠すためだろうな、そのくらいは僕でも分かるんだ、とぼそぼそ考えた。早苗さんはしばらく目がうつろだったが、だんだんいつもの調子を取り戻してきた。
化粧が濃いな、と僕は思った。泣いていた顔を隠すためだろうな、そのくらいは僕でも分かるんだ、とぼそぼそ考えた。早苗さんはしばらく目がうつろだったが、だんだんいつもの調子を取り戻してきた。僕は、早苗さんを描きたい、と言った。早苗さんはただ、いいよ、とだけ言った。 雨が降り始めたようだった。傘持ってこなかったな、とぼんやり考えながら、僕は早苗さんを描いた。早苗さんには後ろを向いてもらった。きれいな長い髪を、いつまでもじっと見ていたかった。静かな部屋に、遠慮がちな雨音と、鉛筆が紙の上をすべる音だけが、あった。 2003.3.28. 工房の主人 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『恋愛小説家』 |