| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『ライオン・キング』 |
|
|
| 『ライオン・キング』 |
|---|
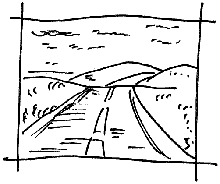 サトルは途方に暮れていた。「糞詰まりだ」。サトルは乾いた頭で考えた。自分がどこにいるのかも、はっきりしなかった。サトルはニュージーランドの地図を広げた。北島の下の方。分かるのは、それだけだった。
サトルは途方に暮れていた。「糞詰まりだ」。サトルは乾いた頭で考えた。自分がどこにいるのかも、はっきりしなかった。サトルはニュージーランドの地図を広げた。北島の下の方。分かるのは、それだけだった。ワーキングホリデーでニュージーランドに来て半年経った頃、サトルは急にヒッチハイクを始めた。「一番北の先っぽに行きたいんだけど、お金がなくなってきたんだ。」出会ったオランダ人にそう言うと、ヒッチハイクしなよ、と彼はあっさり言ったのだった。 首都ウェリントンは北島の一番南にあり、サトルはそこを出発点に選んだ。最初は恥ずかしかった。親指を立てて腕を突き出した途端、全ての車のドライバーが自分を一斉に見るような気がした。 車は全く止まってくれなかった。サトルから離れた所に背の高いやせた西洋人が一人、同じように腕を突き出していた。彼の堂々とした態度に、また引け目を感じた。 と、彼の前に車が止まった。うれしそうに乗り込んでいく彼が、チラ、とサトルを見た気がした。頭がカッとなった。気が付くとサトルは走っていた。 西洋人が立っていたと思われる同じ場所に立って数分後、一台の古い車がサトルに吸い寄せらるように止まった。立っていた場所が悪いのだった。車が止まれるスペースの十分ある場所に立ったらいいよ、とサモアからの留学生たちは言った。車には4人乗っていて、にぎやかにサトルを迎えてくれた。みんな名乗って握手を求めてくる。ドライバーもこっちを見て手を伸ばしてきたので、サトルは「前を見て!」と笑って叫んだ。興奮して、とにかくしゃべりまくっていた。 面白いように車は止まった。世界中を回ってる、というあやしげなおじさんが乗せてくれた後は、日本に一度だけ行ったが、帰りに日記帳をなくしてしまい、それが残念でならない、というおじさんだった。絶対探してみせます!とサトルが真面目な顔で言うと、もういろんな手を尽くしたんだ、期待させるのはやめてくれよ、とおじさんは前を見てつぶやいた。 無口な兄ちゃんとは、まったくしゃべらなかった。でも笑顔で別れた。 サトルには気持ち良かった。 頭の上に延々と広がる青い空が、サトルを包み込んでくれてるようだった。 しかしサトルの運は、ぷつりと悪くなった。地図をいくら見ても、自分がどこにいるのか、正確に分からなかった。ドライバーに行き先を聞かれるたび、サトルは「北へ」とだけ答えていた。道順なんてどうでもいいよ、ニュージーランドの先っぽに行ければいいんだ。 さっきまで青いと思っていた空も、よく見ると黄色くにごっていた。車もあまり通らず、そしてまったく止まらなかった。 歩こう。 止まっているのが悔しかった。背中のバックパックも、重さが増していくような気がした。下を見て一歩一歩足を交互に出す。サトルのあごから滴り落ちる汗が、乾いた大地に落ちるたびに小さな土ぼこりを作っていた。 辺りが薄暗くなる頃、小さなトラックが数メートル先に止まった。小柄なおじさんが降りてきて、サトルを見た。 「ヒッチハイクか?」 サトルはやる気なく、腕を突き出したまま歩いていたのだ。 テントがあるから、と何度か断ったが、おじさんはサトルを家に連れていってくれた。「うちのおちびちゃんが寝てるから、静かにしててくれな。」家に入る時、彼は言った。 サトルは彼と二人で、用意してあった夕食を食べた。食べながら、ヒッチハイクや旅の話をした。食べ終わると、彼は働いてる奥さんを迎えに出ていった。サトルが食べたのは、彼女の分だったのだ。 「日本には小さい頃、行ったことがあるのよ。」とめがねをかけた奥さんはパンをかじりながら言った。夕食を食べてしまったことに少し心が痛んみつつ、お互いめがねをかけているのでサトルは親近感を持った。「また日本に行きたいなあ。でもね、彼の得るお金じゃあきっと無理ね。」彼女はチラ、と 洗い物をしている夫を見た。 小さな女の子はかわいかった。部屋中におもちゃが転がっていて、でも女の子はサトルに興味を持ったようだった。サトルはどうしていいか分からず、ただ近付いてくる女の子に向かってニコニコするだけだった。 おじさんがラジオをつけた。大人が3人でいっぱいになる程の大きさの部屋に、心地よいポップスが静かに、満ちた。 奥さんが段ボール片をくれた。「ここに行き先を書いて立つと、車がよく止まってくれるわよ。」サトルはペンを借りて、大きく「North(北へ)」と書いた。 おじさんがおもむろにビデオを出してきた。『ライオン・キング』だった。「まだこの子は言葉が分からないけどね、でもこれが大好きでよく見てるんだよ。見るかい?」サトルは、見たことないから見たい、と答えた。 日本では、一歩踏み出すともうすべてが決まってしまって、後戻りができなくなるという不安にいつもかられていた。何もかも嫌だ。一人になりたい。サトルは、日本を出た。 そして今、サトルは見ず知らずの家庭でくつろいでいる。 サトルはとまどっていた。 心地よかったのだ。 女の子は途中で眠り始め、奥さんが寝室に連れていった。続いて、おじさんも向かった。おやすみなさい、と言う前に、「ビデオが面白い」と言った。彼は満足そうにうなづいた。 サトルは一人で最後まで見て、寝袋にくるまって寝た。 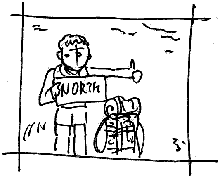 目覚まし時計をセットしておいたのに、寝過ごしてしまったようだった。すでに日は高かった。慌てて起きたが、すでに家には誰もいなかった。
目覚まし時計をセットしておいたのに、寝過ごしてしまったようだった。すでに日は高かった。慌てて起きたが、すでに家には誰もいなかった。サトルは言われた通りに、パンを焼いてバターを塗って食べた。コーヒーも一杯飲んだ。それから、部屋の隅に新聞の束を見つけ、それを一枚破って大きなツルを折った。 羽のところに、「Thank You Very Much, Satoru」と書いた。 サトルは、「North」と大きく書かれた段ボール片を小わきにかかえて、家を出た。 2003.3.22. 工房の主人 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『ライオン・キング』 |