| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『レディ・ホーク』 |
|
|
|
『レディ・ホーク』
|
|---|
|
だが武志が仕事を終えるよりも早く出勤してくる女性がいた。ホワイトカラーらしく、きちんとスーツを身に着けた彼女は、始業時間より一時間以上も前に姿を見せる。シャッターが閉まったままの正面玄関ではなく、武志のいる警備員室へと続く、通用口を通るために差し出された社員証には開発部・三浦有希とあった。
夜勤に就いた長い夜、武志はなかなかピースの揃わないジグソーパズルに挑むように、古い記憶を並べ替えてみた。おぼろげな外枠から、映像が姿を現し始める。
空がうっすらと白み始めた頃、記憶の最後のピースが揃った。映画のタイトルが浮かび上がると同時に、古い映像までもが動き出す。
だが、有希を気にかけるようになった武志の視界には、たびたびその姿が目に留まるようになった。 そんな小さな秘密が少しづつ武志の胸に貯まって行ったある日、自分の企画が通らなかったと、くやし涙を流しながら誰かに電話をしている有希を見かけた。
そして、武志はひとつの賭けをした。 家に帰ればすぐふとんに潜り込むしかない武志だったけれど、その日は一日中、落ち着かない気持ちで過ごした。
|
| 映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】 All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『ら〜ろ』 >『レディ・ホーク』 |
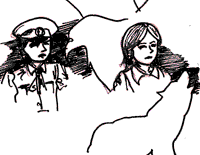 武志の一日は朝陽とともに終わる。
武志の一日は朝陽とともに終わる。