|
ホーム>
映画にまつわるものがたり>
『は〜ほ』 >『ベルベット・ゴールドマイン』 |
|
|
| 『ベルベット・ゴールドマイン』 |
|---|
 デビューが決まったら、貴見のイメージを変えて行くよ。それでいいね?
デビューが決まったら、貴見のイメージを変えて行くよ。それでいいね?打ち合わせの席で俊介にそう言われた時、貴見はそっぽを向いたまま、「ああ」と返事をしただけだった。 「好きにすればいいだろ。俺が嫌だって言っても、どうせ聞いちゃくれないんだから」 いつからだろう。こんなふうに互いに眼を逸らしあってものを言うようになったのは。 喧嘩にさえならない。大人、だから。同じ場所に立ってしまったから。もう我侭を言える子供ではいられない ―――。 少なくとも俊介に声をかけられた時は違っていた。それまで、小さなライブハウスで好きな歌だけ唄っていた貴見は、気に入らないことがあれば逆らってもみたし、ふて腐れてもみた。けれど、俊介は自分をプロデュースする立場の人間で、貴見は言われるがままその全てを受け入れるしかなかった。逆に言えば、俊介が指し示す方向に向かって自分なりのやり方で唄っていればいい子供だった。 貴見のデビューの話が持ち上がり、俊介に方向性を変えるかも知れないと言われた時も、今まで自分がしてきたことに蓋をしてどうするつもりなんだと、何度も真正面からぶつかって、さんざん話し合った。 「変えるって言ってもね、前向きに考えたことだから。変化、なんだよ貴見。今までとは違った貴見を見せるっていうか…サウンドにも幅を持たせて、これまでとは違った曲調を打ち出してみようかなって思ってる。その他のこともいろいろ考えてるから」 俊介は聞き分けのない子供に言い聞かせるように貴見の眼を覗き込みながら何度もくり返した。今までとは違うことをして、もっと前に進むためなんだよ。 「変化って何だよ。あんたの言ってることよく判んない。今までと同じじゃなんでいけねえの? 俺はこのままずうっと、今までと同じように唄ってられればいいだけなのに」 デビューしたらしばらくは露出を控えて、と言った俊介の一言に貴見が食い下がる。唄えなくなるのは嫌だ。それを自分から取り上げてどうするつもりなんだ、と。 「新しいこと始めるには貴見の今までのイメージが強すぎるし。だからしばらくの間はね。…でもそれもそんなに長くはないから。それに…ぼくも一緒だから」 「あんたが一緒にやるってどういう意味だよ。同じユニットになるとでも言うの?」 正面切って叩き付けた貴見の言葉に、俊介はあっさりと頷いた。 そうだよ。同じユニットで、一緒にやるんだよ、貴見。 その一言で折れた。 名の知れたプロデューサー結城俊介。知り合って以来、ずっと俊介の影を追って来た。 追いつきたい。そして追い越したいと思ってずっと走って来たような気がする。 いつも後ろに、あるいは隣に。視線を向けた先に俊介がいる。それだけでよかった。それが、よかった。意に染まない楽曲も、一人歩きして行くイメージも、変えられて行く自分でさえも受け入れた。二十四時間、どんな時もこの人を独り占めしているのは自分なのだと思うと嬉しかった。 何かが違うと感じ始めたのはどちらが先だったのだろう。貴見は、ある日ふと気づいたのだ。追い越したはずの影が自分の足元にある。踏んでも踏んでも逃げてゆくそれがもどかしくて。自分は果たしてそれを超えられたのかと思うと不安になって…意味もなく俊介に当たってしまったりもした。その度に激しい後悔が襲って来る。そして、そのとたんに気づくのだ。足元に揺らめいていたのは自分の影だったのだ、と。 『才能ならごろごろしてる。伝説の人になれるかどうかだ』 ベルベット・ゴールドマイン。デビッド・ボウイの曲からタイトルを取った映画にそんなセリフがあった。グラムロックの世界に生きたブライアン・スレイドとカート・ワイルドにデビッド・ボウイとイギー・ポップの影を絡めた映画だった。頭の中で四人の影が絡み合って騒ぎ出す。伝説になんてならなくていい。自分はただ歌いたいだけなのに、それがなぜこんなにも難しいのだろう。貴見は客が帰った後のステージに立ち尽くして、そればかりを考えていた。 「なぁ。俺、どうしたらいいかよく判んない時があんだよ。はっきりああしろこうしろって言ってくれた方がどれだけ楽か知れないのに、あいつははっきり言わねえし。今日もさ……」 昔の仲間にこぼしてみたところで、メジャーデビューという花道に立ってしまった貴見に、彼らはどこかそっけなかった。 「そんなこと言ったって、俺らがどうこう言えるもんでもないし。結城さんとちゃんと話した方がいいんじゃないの?」 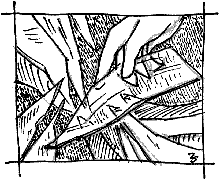 壊してしまおう。揺らめく影に追いかけられるこんなガラスのステージなんか。イギー・ポップが砕いたガラスで自分を傷つけたのなら、俺はこのステージごと叩き割ってやりたい。いっそ粉々に砕けてしまえばいい。やつと一緒に立っているこの場所が。
壊してしまおう。揺らめく影に追いかけられるこんなガラスのステージなんか。イギー・ポップが砕いたガラスで自分を傷つけたのなら、俺はこのステージごと叩き割ってやりたい。いっそ粉々に砕けてしまえばいい。やつと一緒に立っているこの場所が。震える指先でその破片を拾い集める。とたんに指先から血が吹き出す。かまわずに手のひらの上のそれを握り締める。ぽたぽたと落ちるのは自分の血なのか。それとも後悔の涙なかも、もう判らない。 だけど、どんな小さなかけらひとつも見失わないように。ひとつも失くさないように。俊介が歩み去ったステージの上で、貴見は血まみれになりながらその破片を拾い集める。 ここは、ガラスのサンクチュアリ。誰も侵すことのできない二人だけの場所。だから…。 自分が変えられて行く。それならそれでもいい。けれど、ガラスの欠片はひとつ残らず自分が持っている。それは、この手のひらの中にある。 だから…この破片をひとつ残らず自分が持っていれば、いつかまた昔の自分に戻れるはず。 そうしたら…自分の血の混ざったこのガラスで、今度は影なんか映し出さないステージを創ろう。その時が来たら、二度と割れないガラスで、自分を誰にも壊されないために。 2003.4.12. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
|
ホーム>
映画にまつわるものがたり>
『は〜ほ』 >『ベルベット・ゴールドマイン』 |