| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『は〜ほ』 >『フェノミナン』 |
|
|
| 『フェノミナン』 |
|---|
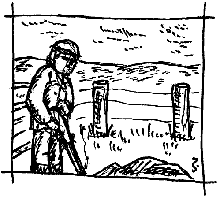 「おいシン、後ろを向くな。」
「おいシン、後ろを向くな。」ロジャーの声がした。え?とシンイチが振り向いた瞬間、パン、と乾いた音がした。 牛が、崩れ落ちた。 デビッドがその前に立っていて、手に握られてる長い銃身の先から細い煙が立ち上っていた。 「見ちゃったな。」 ロジャーは苦笑いしながら言った。「シン、あれを片付けてくれ。」 シンイチは指差されたモノを、見た。何だろう、近付く。 それは、飛び散った子牛の内臓だった。うっすらピンクだった。映画の『ゾンビ』は正しいな、とシンイチは思った。 延々と続いてるはずのなだらかな緑の大地は、朝もやでほとんど隠れてしまっていた。季節は確実に冬に近付いていて、息は視界を奪うくらいに真っ白だったが、シンイチの体は汗だくだった。 いつものようにシンイチが子牛の出産に立ち会っていて、そこで子牛は半分体を出して、死んでしまった。獣医が呼ばれ、子牛を切断することになった。シンは見ない方がいい、と別の仕事を頼まれ、シンイチがそれを終えて戻ったところで、母親牛を撃ち殺す現場を見てしまったのだった。 ブレックファストにしよう、とデビッドが言い、シンイチはその後に続いた。 ドゥ、と倒れるんじゃないんだな。パタン、と"落ちる"んだな。 シンイチが先ほどのことを思い出しながら家に着くと、ノーマが朝食をテーブルに並べていた。 皿には、大きなソーセージが3本ずつ乗っている。ロジャーがにやりと僕を見た。 うわあ、とシンイチは思ったが、腹の減り具合は、簡単にそんな意識を吹き飛ばしていた。 シンイチはニュージーランドにいた。住み込みで、広い広い牧場で働いていて数カ月が経っていた。大学を休学し、「何か」を探すために外国に来た。留学でも旅行でもなく、「ワーキングホリデー」というビザがあることを知ったのだった。これがあれば、現地で働くことができる。 しかし現実には、仕事なんてあまりなかった。あるのは肉体労働ばかり。でもシンイチは嬉々として働いた。今までやったことないことをする。そこに「何か」があるのかもしれない。 日本では怠惰な生活を数年続けていて、シンイチの体はひたすら太っていた。その時は、自分が堕ちて行くのをどこか冷めた目で見ていた。しかし今は違う。体を動かす喜びを知ったのだ。体重は一か月で7kgも落ち、その後は筋肉がついていくに従って体重は逆に少しずつ増えていった。シンイチはよく、夜中に部屋の鏡の前で自分の体を月明かりに照らして悦に入っていた。劣等感の中には消えていくものもある。大きな発見だった。 外国で、シンイチは自己紹介するのが実は嫌いだった。ニックネームは自然と、「シン」になる。sin=「罪」だ。いつも笑われていた。でもそれで覚えてもらえるならいいや、とシンイチはうそぶいた。 牧場での仕事は、慣れるまで必死だった。楽しいとか厳しいとか、感じる余裕もなかった。朝は4時に部屋の電気を付けられて起こされる。辺りは真っ暗で、しかも凍えるように寒かった。シンイチはすぐに洗面所に直行する。冷たい水で顔を洗ってしまう。寒さと眠さのダブル攻撃よりも、眠さを先に取っ払ってしまって、寒さだけに専念したかったのだ。 暖炉は、少しだけ前の晩の温もりを残していて、いつも燃えカスに覆いかぶさるようにして上下のつなぎに着替えた。ここで働きはじめてから、つなぎと長靴を用意してもらった。つなぎは子供用のを借り、長靴は子供用でも大きくて、わざわざ買ってもらった。  少しでも寒さを和らげたくて、毛糸の帽子は視界が半分隠れるくらいまで、深くかぶった。家にはシンイチが起きた時にはもう誰もいない。家のドアを開けるときが、シンイチは一番嫌いだった。寒さがいつも、シンイチに襲いかかってくる。一人で暗闇に出る。シンイチは日本で、これだけの暗闇に出会ったことがない。得体の知れない生き物の鳴き声だけが聞こえてくる。働きはじめてすぐ、デビットが南十字星を教えてくれたが、そんなものを見上げる余裕はなかった。
少しでも寒さを和らげたくて、毛糸の帽子は視界が半分隠れるくらいまで、深くかぶった。家にはシンイチが起きた時にはもう誰もいない。家のドアを開けるときが、シンイチは一番嫌いだった。寒さがいつも、シンイチに襲いかかってくる。一人で暗闇に出る。シンイチは日本で、これだけの暗闇に出会ったことがない。得体の知れない生き物の鳴き声だけが聞こえてくる。働きはじめてすぐ、デビットが南十字星を教えてくれたが、そんなものを見上げる余裕はなかった。遠くに明かりが点となって見える。デビットとロジャーがそこで搾乳をしている。その明かりだけをたよりに、シンイチは暗闇の牧場を横切っていくのだ。しばらく歩くと、低いうなり声が近付いてくる。牧羊犬のグルースだ。犬がひどい扱いを受けるこの国で、シンイチはすぐにグルースと仲良くなった。ただこいつは、四つん這いになったシンイチよりも大きく、しかも真っ黒な毛をしていて、どこからともなく暗闇から飛びかかられる前に、いつもシンイチは身構えた。 牛舎に着くと、デビットがすでに乳を搾っている。おはようございます、と叫ぶのと同時にシンイチもすぐに作業に入る。働きはじめて2週間で、搾乳機だけは触れるようになった。搾乳場の片側に20頭ずつ、両側で40頭の牛のお尻がずらっと並んでいて、片っ端から搾乳機を4本ずつ取り付けていく。牛が尻尾を上げると要注意だ。勢いよく尿や糞が降ってくる。頭をかがめて搾乳機をつけながら、腹部を蹴ってくる足に注意し、頭の上のジョバージョバーやドッボドッボにも気を付けなければならなかった。 搾乳は一日に2回行う。昼は午後2時頃だ。これは寒くなくて、余裕があった。搾乳は全部任され、シンイチはよくラジオを聴きながら鼻歌を歌っていた。洋楽には初めて触れたが、聴いているとなかなかにシンイチの性に合ってるようだった。 その中で一曲ものすごく気に入ってしまった曲があった。DJが何やら説明しているのだが、何しろ英語が早くて聞き取れない。毎日毎日聞いているうちに、どうやら『チェインジ・ザ・ワールド』という曲名らしいということが分かった。歌うのは、エリック・クラプトン。ああ、そいつを知ってるぞ、聞いたことあるぞ、とシンイチは思った。曲の説明は、分からなかった。 夜はみんながテレビを見ている横で、小さなノートに覚えた単語をメモっていた。発音は、自分なりにカタカナで書く。牧場用具は、全部イラストで描いた。時々やってくる、デビットの孫娘に、本を読んでやったりもした。こんな発音で教えてもいいのだろうか、と思ったりもしたが、まあいいや、と思った。発音が悪い分、お化けや悪者の台詞には感情込めた。彼女は大喜びだった。 朝がいつも早く、夜は8時には眠くなってしいたが、やがて絵の具を買ってきて水彩画を描くようになった。部屋にあった、「ナショナル・ジオグラフィック」に絵心を動かされる写真が数多く載っていたのだ。 デビットの家と、その息子ロジャーの家は牧場内にあった。いい人ぶって、しかしどこか日本人を見下している人間は多かったが、ロジャーたちは人間的にシンイチに接してくれた。彼らはよく日本人をネタにして笑ったが、ちっとも嫌みではなかった。 働きはじめて2か月と10日目に、シンイチはついに、糞を浴びてしまった。 毛糸の帽子があるために、すぐには分からなかった。急に頭が重くなり、よろめいた。シンイチはあわてて安全地帯まで走った。「くそ!くそ!」と英語で叫んだ。デビットが大笑いしていた。 英語でも日本語でも、おんなじ「くそ(shit)」と叫ぶんだな、と帽子を洗いながら何だかうれしかった。 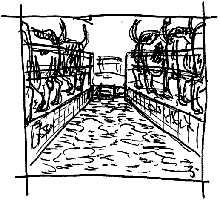 シンイチは日本にいる時、どこかやはりおかしかったのだ。数少ない友人とも口をきかなくなっていて、家に何か月もこもっていた。ニュージーランドに来ることも、誰にも言わず、アパートを引き払った。俺はどうなるんだろう。景色はいつも、灰色だった。
シンイチは日本にいる時、どこかやはりおかしかったのだ。数少ない友人とも口をきかなくなっていて、家に何か月もこもっていた。ニュージーランドに来ることも、誰にも言わず、アパートを引き払った。俺はどうなるんだろう。景色はいつも、灰色だった。帽子についた牛の糞を洗い流しても、それをまたかぶる気にはなれなかった。ようし、帽子なしでやったろうじゃないの! シンイチは青い空と緑の牧場の中にある牛舎にもう一度挑んでいった。 お馴染み、エリック・クラプトンの「Change The World」。映画『フェノミナン』の主題歌として使われてます、とDJが言った。 今度ははっきり、聞き取れた。 2003.4.10. 工房の主人 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『は〜ほ』 >『フェノミナン』 |