|
ホーム>
映画にまつわるものがたり>
『は〜ほ』 >『バッファロー66』 |
|
|
| 『バッファロー66』 |
|---|
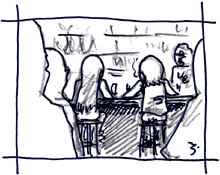 クラブがまだナイトクラブと古風な呼び名で呼ばれ、それ以上でもそれ以下でもなかった頃。小さな基地の街のダウンタウンまで抜ける坂道の途中に、そんな小さな店があった。煙草と酒の匂い、そして男たちの粋な口説き文句と女たちのささやき声で埋め尽くされたその場所は、俗悪でふしだらで、いつも親しみにあふれていた。
クラブがまだナイトクラブと古風な呼び名で呼ばれ、それ以上でもそれ以下でもなかった頃。小さな基地の街のダウンタウンまで抜ける坂道の途中に、そんな小さな店があった。煙草と酒の匂い、そして男たちの粋な口説き文句と女たちのささやき声で埋め尽くされたその場所は、俗悪でふしだらで、いつも親しみにあふれていた。その夜も、ナナとキムは音の洪水に身を沈めて、投げかけられるいくつもの誘い言葉を適当にあしらいながら、いつもの週末を過ごしていた。 「こういうとこだとラップ聞く気にもなるけど、私やっぱりベイビーフェイスがいいな」 ナナが少しばかりうんざり、といった様子で言う。するとすかさずキムが口を挟んだ。 「うわ、それって前の男の影響? ちょっと前まではトゥパックが最高とか言ってたくせに」 「いいの! そういうあんたはなんなのよ」 「え? 最近はバックストリートボーイズかな」 「ミーハー過ぎない? アイドルじゃん」 「だってかわいいんだもん」 そこで2人は顔を見合わせてぷっとふき出した。けれど曲の好みが分かれるように、ナナが選ぶのはいつもアフリカ系のアメリカ人で、キムの彼氏は白人だった。この界隈では男の種類が違うと女友達の種類も変わることが多かったけれど、ナナとキムは「そんなのはバカバカしいこと」だと思っていた。 それを言うならナナは日系だけれどキムは韓国系だ。人種で選ぶなんてちゃち過ぎる。2人はいつだって、自分の側に近づける相手をテイストや会話の技術で選んでいた。だから薄暗いクラブの中で、2人がお互いを「同類」だと感じるまでに時間はかからなかったのだ。 「そういえばこないだ彼の部屋で映画見たんだけどさ。バッファロー66って、ヴィンセント・ガロが出てるやつ」 「へえ、知らない。それって白人の俳優? どんな映画?」 ブラックムービーしか見ないナナが首を傾げる。 「何かラテン系の白人。…でね、ガロのお母さんがさ、ナントカってフットボールチームが優勝した日にガロを産んで、その試合を見れなかったってずっと文句言ってるの。自分の息子よりフットボールの方が大事って、もろアメリカ人だよね」 そこから2人は、ケチャップをかければ何でも食べれる、とか、とりあえず大きな家と高級車を欲しがる、などといった「ティピカルなアメリカ人」をあげつらっては笑い転げた。 しばらくして、新しい飲み物のグラスを運んでくれたウェイターにチップの1ドルを渡した後、ふと横を見るとそこに彼はいた。 「次の飲み物はぼくに買わせてくれないかな。ぼくの名前はアレックス。隣にいても構わない?」 褐色の肌を持ったその男はおずおずとナナに声をかける。すかさずキムがナナを肘で突つく。 「彼、けっこういいじゃない」 女の財布をアテにするような男が増えてきた中で、その彼は野暮ったい服の中に正統なやり方を隠し持っている。ナナは、さもどうでもいい、といった様子で椅子を指差しながらも彼が自分の隣に座ることを許した。 そして、二つ折りにした紙幣をつまむ指の品の良さと、自分ではそれに気づいていない無頓着な様子が気に入って、キムが帰った後もアレックスと2人で話し込んだのだった。 だからこそ、店がクローズした後の帰り際になって、アレックスが「ぼくの部屋に来ない?」と言い出した時、ナナは少しばかり失望したのだ。 『結局はそういうことなわけ?』 けれどナナだって子供というわけでもない。ましてや今はステディがいるわけではないのだし、誰に文句を言われることもない。今からキャブを拾って帰るのも面倒だし、始発の電車を待つなんてまっぴらだった。 そう思ったナナは肩をすくめて立ち上がる。アレックスの車に乗り込む時でさえ、彼はきちんとナナのためにドアを開けてくれた。 『あんなことさえ言い出さなければ完璧なのに…』 車の助手席に収まりながら、ナナは隣の男を残念な気持ちで見つめていた。 けれど所詮は同罪なのだ。部屋に誘った男。それを承諾した女。そこで公式はできあがる。どちらも相手を非難することはできない。いや、軽蔑しあうと言うべきか。  部屋に着いて、セオリー通りに飲み物を振舞われ、互いの間に流れる空気の濃さを計る。それがとろりとした蜂蜜のようになった午前3時過ぎ、アレックスは突然こんなことを言い出したのだ。
部屋に着いて、セオリー通りに飲み物を振舞われ、互いの間に流れる空気の濃さを計る。それがとろりとした蜂蜜のようになった午前3時過ぎ、アレックスは突然こんなことを言い出したのだ。「ここまで来てももらって申し訳ないんだけど、まだしなきゃならないことがあるんだ。眠かったら先に寝てて。ベッドは隣の部屋だよ」 ベッドを貸す代償を当然求められるとばかり思っていたナナの頭の中にはとたんに疑問符が飛び始める。そんなナナにはかまわず、アレックスはTVのスウィッチを入れた。 その瞬間、ナナは、自分がキムの言っていた映画の主人公の立場に立たされたことを知った。彼の言う「しなければならないこと」とはフットボールの衛星中継に見入ることだったのだ。 「あの店にいたら見られないし、でも今日はバイキングスの試合があったし。でもきみとももう少し一緒にいたいなって思ったから。だから…ごめん」 申し訳なさそうにつぶやいたアレックスに、ナナはおずおずと訊ねる。Tシャツ…借りてもいいかしら? もちろん! 途端ににこやかな瞳が答える。 あのね、と言いかけたナナの声はゲームの開始を告げるホイッスルの音にかき消されてしまい、ナナは楕円形のボールよりも価値のない自分を感じていた。 けれどガロの母親のように、彼に文句を言う気にはとてもならならず、こんな裏切りならいくつあってもいいと、食い入るようにTVの画面を見つめている彼をその場に残して、幸せな気分でベッドに潜り込んだのだった。 2003.8.12. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
|
ホーム>
映画にまつわるものがたり>
『は〜ほ』 >『バッファロー66』 |