| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『た〜と』 >『ツインズ』 |
|
|
| 『ツインズ』 |
|---|
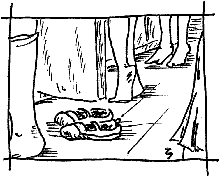 ロッカールームの中には、いくつもの秘密が潜んでいる。十五歳という大人と子供の真ん中に立たされた少女たちから放出された、数え切れないほどのゴシップは、デオドラントスプレーやオードトワレの匂いと混ざり合って空気の色さえも変わって見えるほどだ。
ロッカールームの中には、いくつもの秘密が潜んでいる。十五歳という大人と子供の真ん中に立たされた少女たちから放出された、数え切れないほどのゴシップは、デオドラントスプレーやオードトワレの匂いと混ざり合って空気の色さえも変わって見えるほどだ。そんな空気の中で、誰かが急に声を上げた。 「…だからぁ、この前の日曜日、うちのママがいなかったからさぁ」 ね、ね、ね、それでどうだった? 何が? そこまで言っといてとぼけないでよ。 矢継ぎ早に質問を浴びせかけられているのは…ああサブリナ。彼女はクラスの中でも眼を引く早熟な子で、いつも噂の中心にいた。その噂通りのトランジスタグラマー……。 メイ・リーは、あからさまな告白話にわずかなうっとおしさを感じて彼女から目を逸らす。その先にはいつもアンジーがいた。 バスケットのチームでポイントゲッターのアンジー。ブロンドの髪をばっさりとショートにして、頬にはそばかすが浮かんでいる。きれいに伸びた長い手足。大きくて蒼い瞳。どれもメイ・リーの持っていないものばかりだった。 同じ女の子で、同じ十五歳なのに。まるでツインズに出て来た、似てない双子のジュリアスとヴィンセントみたい。 そんなふうに思って、メイ・リーはふとため息をついた。 いつだって溌剌としていて、明るく笑うアンジー。彼女には悩みなんかないみたいで、そんな彼女を見ていると、羨ましい気持ちの反面、彼女の周りを取り囲む乾いた空気に安心するのだ。 そんな彼女の様子がおかしいと気づいたのは、それから何日経たない頃だった。 窓の外をぼんやりと眺めていたアンジーの瞳が、うっすらと膜がかかっていたようになっていたのをメイ・リーは見逃さなかった。その横顔はいつもと変わらずきれいだったけれど、快活なはずの彼女を取り囲んでいるのは、サブリナや、あるいは自分と同じ、少女から大人へと変わって行く過程で放出される種類の匂い。それは、メイリーが今まで避けて来た類のものだったのだ。しっとりと濡れたような雰囲気に包まれた、どことなく心もとなげに見えるアンジーの様子は、まるで鏡に映った自分を見ているようで、メイ・リーはその時、なぜか悲しくなって慌てて眼を逸らしたのだった。 そんなある日の放課後、ロッカールームに忘れ物をしたメイ・リーがドアを開けると、ベンチに腰を降ろしたアンジーがいた。 「アンジー…?」 そっと声をかけると、アンジーは慌てて頬を拭ってから顔を上げた。けれど目の縁には隠し切れない涙の後が残っていて、それを認めたメイ・リーの足が凍り付いた。 変なとこ、見られちゃったね。さらりと言おうとした語尾が震えている。明るい表情の下に泣き声を押し込もうとするアンジーの様子に、メイ・リーの胸がせつなく痛む。 「どう…したの……?」 別に。何でもない。Nothing. Iユm O.K. Here is no problem. 「何でもないなら…どうして泣かなきゃならないの? 何で? どうして?」 アンジーの視線が一瞬、宙をさまよい、そしてその瞳には再び涙が盛り上がる。 ……優しい人だって、思ったの。なのに私、つまんないことで怪我までして…ゲームにも出られなくなって……ばかみたい。 「優しい人?」 訊き返したメイ・リーの言葉に小さく頷きながら、アンジーはぽつぽつと話し始めた。 一ヶ月くらい前に、プレゲームでバートラムハイに行ったの。隣のコートではボーイズのチームが試合をしてた。インターミッションの時に、サンドウィッチを食べてた私に、彼が声をかけたわ。それで私の持ってたランチボックスの中身をつまんで言ったの。おいしいね、きみが作ったの? って。そうよって言ったわ。うちのママ、働いてるから自分で作ったのよって。そしたら彼、さすが女の子だね、こんど俺にも作ってよって。彼が私にそう言った時、私、どうしたと思う? メイ・リーは黙って首を振る。アンジーは苦笑いで答えた。 嘘つき、あんたなんか大っ嫌いよって、転がってたボールをぶつけながら何度も言ったわ。そしたら彼、笑いながら逃げ回って、女の子なんだからそんな言葉使うなよ。レディには似合わないぜって。ねえメイ・リー、その時の気持ち判る? メイ・リーは答えず、ぎゅっと自分の手を握り締めた。 泣きたいほど嬉しかった。嬉しかったけど、どうしようもないくらい悲しくて、でもその日は私、なかなか眠れなかった。なのに…それなのに……。 「……なのに…どうしたの……?」 恐ろしい告白を聞くようにメイ・リーが呟くと、アンジーは苦しい物を吐き出すように言った。 ………昨日、見たの。彼のこと。隣には女の子が歩いてた。肌がチーズケーキみたいに白い、背なんて彼の肩までもなさそうなかわいい子だった。 「そんな…そんなことって……」 もういいのよ。結局そんなもんよね。言葉とは裏腹にその眼からはとめどもなく涙が溢れて来た。明るくて、悩みなんてないと思っていたアンジー。その彼女が人目につかないこんな場所で、たった一人で泣いていたなんて。悩んだり迷ったりするのは自分だけだなんて、どうして思ったんだろう。アンジーだって同じ女の子なのに…。 「私、あなたのスレンダーな体も、長い手足も、そばかすも…全部好きよ」 「メイ・リー……?」 顔を上げたアンジーの眼を見ながら、今度ははっきりと言う。Donユt you know? Iユve been in love with you for a long long time.ずっと好きだったのよ、知らなかった? 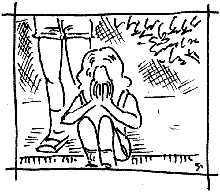 だからこんなところで泣いてちゃだめよ。そうだ、少しだけ髪を伸ばしてみなよ。それで飛びっきりゴージャスな女の子になってプロムに行こう。あなたなら絶対になれるよ。だって私たちはまだ十五歳。階段の前に立ったばっかりだもん。これからどうなるかなんて、誰にも判らないじゃない?
だからこんなところで泣いてちゃだめよ。そうだ、少しだけ髪を伸ばしてみなよ。それで飛びっきりゴージャスな女の子になってプロムに行こう。あなたなら絶対になれるよ。だって私たちはまだ十五歳。階段の前に立ったばっかりだもん。これからどうなるかなんて、誰にも判らないじゃない?「……そうね。そうかもね」 勢い込んだメイ・リーの言葉に頷いて、アンジーがゆっくり立ち上がる。隣に並んだ彼女は自分よりずっと背が高いけれど、でも同じ女の子なんだと、メイ・リーは思った。 そして……。ロッカールームの中には、またひとつの秘密が重なった。けれどそれを知っているのは二人だけなのだと思うと、メイ・リーは嬉しいようなくすぐったいような気持ちになって、隣を歩くアンジーの横顔に、そっと微笑みかけたのだった。 2003.4.23. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『た〜と』 >『ツインズ』 |