| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『た〜と』 >『太陽と月に背いて』 |
|
|
| 『太陽と月に背いて』 |
|---|
 始まりは、声だった。あの日からずっとその声はぼくの耳に、脳裏に、魂の奥底に取りついて落ち着かない気分にさせる。何かを訴えかけて来るようなその声は、確実に何かを狂わせてゆく。
始まりは、声だった。あの日からずっとその声はぼくの耳に、脳裏に、魂の奥底に取りついて落ち着かない気分にさせる。何かを訴えかけて来るようなその声は、確実に何かを狂わせてゆく。あの日。ぼくが初めて彼と出会った日。彼はポケットに手を突っ込み、かったるそうな様子でスタジオに入って来た。あいさつもそこそこにちょっと歌ってみてとサンプル用の譜面を手渡すとあ、はいとかなんとか口の中でもごもごとつぶやいただけだった。 その様子から、ぼくはどうせまただめだろうと、諦めに似た気持ちでブースに入ったのだ。今までに何十人も通り過ぎて行った「アーティスト」と名乗る人間たちのように、彼もまた、同じようにぼくの前から消えて行くのだろう、と。 なのに、その声が耳に飛び込んできた瞬間に鳥肌がたった。 もしかしたら…いけるかも知れない。 初めて「やっとみつけた」と感じた。小さな体のどこにそんな力があったのかと思わせるその声は、周囲にある何をも震わすことなくただひたすら真っすぐに、ぼくへと突き進んで来た。やっとみつけた。それは確信にも近い「可能性」を限りなく秘めていた。 けれど次に待っていたのは、その声の持ち主のこんな言葉だった。 「ダメならダメで早いとこ言ってもらえます? 俺もいろいろ忙しいんですよ」 オーディションに来る誰もが頭を下げ、どうそよろしくお願いしますというのが普通なのに彼は違っていた。 生意気な子だと思った。けれど、歌っている間はあんなに生きていた彼の、その後の投げやりな様子にも興味を引かれた。そして相手が生意気だというだけで手放すには、その声はあまりにも力がありすぎた。 そして彼はぼくの近くにいる人間になった。 たいしたプロモ−ションもせずに、小さなライブハウスで唄わせたことも、キャパシティの小さな会場で数をこなすスケジュ−ルを組んだことも、すべては彼に対する挑戦だった。 どこまでついてこられるか。 そんな気紛れともいえる要求のひとつひとつに振り回されながらも、それでも彼は、その全てを乗り越えてきた。体中傷だらけになって、見えない血を流しながら。 ステージでの彼は、その体に流れる音楽を水に、そして自分に向けられる歓声を糧にして鮮やかに咲き誇る大輪の花だ。けれどもそのふたつがない場所では、まるで精彩を欠いたように色あせてしまう。唄うことを取り上げてしまったら、きっと生きては行けないだろうと思わせるほどにその変わり様はあからさまだった。 そして彼は泣く。初めて自分だけのステ−ジにたった日。それから何度となくステ−ジの真ん中でそれこそ歌えなくなるほどに泣きじゃくる。自分にはできない、と思う。音楽に対する情熱は同じでも、ぼくにとってのステ−ジは、自分の音楽を披露する場であり、あくまでもエンタ−テイメントの場所なのだ。けれど彼は……彼にとってのステ−ジは、自分の生きる場所であり、自分が生きていることを確認するための場所なのだと、いつしか気づかされていた。 それだけの体温を感じることは、ぼくにとっても喜ばしいことだった。けれどもその反面、どうしても消せない想いもあるのだ。 それはきっと、往年の詩人で年老いたヴェルレーヌが、ランボーに感じた想いと同じ種類のものだろう。認めたくはなかったけれど、それは紛れもない「嫉妬」だった。なのに彼は、ぼくに対してプロデュ−サ−に対する以上の感情を持って接して来るようになった。 唄う時と同じ種類の、剥き出しの心でぶつかってくる彼をどう扱えばよいのか、時として判らなくなることがあった。そんな時、ぼくは自問自答を繰り返した。 自分に何ができるだろう。大切だとも思う。そして愛しいとも。けれど相手は自分の商品で、自分は彼を創る者だ。立っている場所が違う以上、同じ立場で愛することは不可能になる。 歌に生き、恋に生き。 彼からそのふたつを取ったら何が残るだろう。歌うことと愛することは彼の中で生きることと同義語なのだ。そんなディーバのような彼を、果たしてぼくは愛しているのだろうか。 自分の持たないものを持つ彼を、初めて怖いと思いながら、拭い去れない嫉妬を感じながら、それでも彼の声に振りまわされているのはぼくの方なのだ。 それに気づいた時に、思い出した言葉があった。 『太陽と月に背いて』という映画で、若くて美しい天才詩人、ランボーに向かってヴェルレーヌがつぶやいた言葉だった。 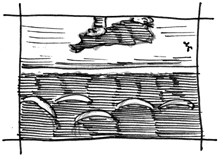 ……私は妻の体より、彼の才能を愛している。
……私は妻の体より、彼の才能を愛している。同じ言葉を、諦めにも似た気持ちで呟いてみた。 ……ぼくは、世の中のどんな女よりも、彼の才能を愛している。 その瞬間にぼくは負けたのだ。 そしてこれから先、二度と自分が彼に勝てることなどないだろうとも思った。 ならば、ぼくたちはひとつのものになってしまおう。体を繋ぐよりもっと近く、もっと確かなものに。 体をすり寄せて、甘くねだるその声は媚薬のようにぼくを惑わせる。彼が生きている時にはいつだってその声がそこにある。 ならば、ぼくはその声を生かすために、全てを捨てよう。 ヴェルレーヌが、ランボーのために何もかもを投げ捨てたように。 2003.4.23. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『た〜と』 >『太陽と月に背いて』 |