| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『さ〜そ』 >『スタンド・バイ・ミー』 |
|
|
| 『スタンド・バイ・ミー』 |
|---|
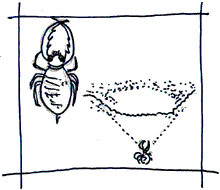 その日は夏休みの真っ最中で、ギラギラした太陽は覚えているけれど、でも暑かったという記憶はない。
僕と神野。2人の小学生は、田んぼのあぜ道を歩いていた。
その日は夏休みの真っ最中で、ギラギラした太陽は覚えているけれど、でも暑かったという記憶はない。
僕と神野。2人の小学生は、田んぼのあぜ道を歩いていた。蟻地獄を捕りにいこう、と言い出したのは僕だった。 テレビで初めて、蟻地獄という生き物を知った時の興奮は忘れられない。砂の上にスリバチ型のワナを作り、そこに蟻が入ったらもう最後。あがいてもあがいても砂は崩れ落ちて上には戻れない。一番底で待ち構えている蟻地獄は落ちてきた獲物の体液を吸い付くし、死骸をぽんと地面にはじき返すのだ。 体長は1センチもない。丸っこい体に6本の足が生えていて、頭に体長の半分くらいの長さを占めるクワガタ虫のような大きな牙がついている。 アリジゴク、という名前が何ともかっこよかった。また、後ろにしか進めない、というのも魅力的だった。 蟻地獄は、人があまり来ない、砂地に生息しているという。父さんに聞くと、蟻地獄がいそうな場所を教えてくれた。ただ、ちょっと遠いから週末に車で連れていってくれると言った。 でも僕は待ち切れず、翌日神野を誘った。 この頃、電話を使った、という記憶がない。直接相手の家に行って、大声で名前を叫ぶ。これが僕らの唯一の連絡方法だった。 神野は蟻地獄を知らなかった。 家に転がっていた、アポロというチョコレートの箱をポケットにねじ込んだ。アリジゴクはこれに詰めてこよう、と思った。 アリジゴクはチョコレートの匂いは嫌いかな、とも思った。 あの頃は、財布なんてもってなかった。時計もなかった。3人とも手ぶらだった。 僕は先頭に立って歩き出した。父さんが教えてくれた場所までどのくらいかかるのか、まるで考えなかった。 道中は愉快だった。太陽が味方をしていてくれた。僕らは笑い続けた。 それまで、車で通ったことがあるだけだった道を、僕らは歩いていた。いつもいつも、窓の外を飛び去っていた光景を、僕らは手中におさめていた。 目に映るものすべてが、遊び場だった。 すでに行ったことのある場所は過ぎていた。しかし初めての場所でも気にならなかった。田舎というのは道がシンプルにできていて、さらに奥に向かう道は、一本だけだった。 家はだんだんまばらになっていく。目指していたのは、山の斜面をくずしてセメント用の土を掘っている場所だった。砂がうずたかくいくつもある場所。 住宅地を抜けると、周りは農家ばかりになっていった。知らない家が並んでいる中を歩くのもなんだかわくわくした。 道沿いにずっと川が流れていて、僕らは靴を脱いで川に入った。冷たい。帽子で川の水をすくい、その水がこぼれる前に自分の頭にかぶった。「ひやぁ!」と神野は叫んだ。「ひやぁ!」と僕も叫んだ。 しばらく、田んぼのあぜ道を進んだ。 神野が突然、おい、と言った。「ちょっと来てみーや」と言うので覗くと、そこには雑巾のような布の固まりがあった。神野を見ると、やつはニヤニヤ笑ってその布を木の枝で拾い上げた。僕が、あ、と思った瞬間、神野は「スケベ!」と叫んで走り出した。待てや!と僕も慌てて追いかける。 鋪装されていない道の両脇にぽつん、ぽつん、と農家がたっていて、山は目の前にどどんと迫ってきていた。神野と僕は拾った木の枝でチャンバラをしながら歩いた。 大声を出しても、気にならなかった。 一軒の農家の前に、塀の代わりに石が積んであった。その石の途中に、僕は一つだけ、横に細長い色の違う石を見つけた。「おい、これ何じゃろ」僕は持っていた木の枝でその石をつついた。 「石」はぐにゅり、と動いた。 僕は声も出さずに全速力で走っていた。 同時に神野も走ってきて、どしたんじゃ、と言った。僕は、まだ持っていた木の枝を、慌てて捨てた。 前方にやがて、掘り進められた山の斜面が見えた時、僕は走り出していた。神野も走った。 やつの方が背も高く、足も長い。あっという間に追いこされ、僕もくやしくてさらに走った。 2人は息をきらして立ち止まった。 目の前には、小高い砂の山がいくつもあった。 言葉が出なかった。 僕はひとつの小山にかけよった。 顔を近付けた。 そこに蟻地獄は、 いた。 いや、いたというより、そこは蟻地獄に占拠されている、と言ってもよかった。 砂山のそこかしこに、ぽこぽことスリバチ型の穴があいていた。 「おった!おった!」僕ははしゃいで、落ちていた小さな木のかけらを拾い、一つの穴を掘った。 「こうやって底んとこを掘るんじゃ!」言葉と裏腹に、僕には神野のことはどうでもよくなっていた。 木のかけらで底をほじくると、一瞬アリジゴクが現れ、そしてすぐに砂の奥にもぐっていってしまった。 「あぁ!」慌ててその後を追って砂を掘ったが、逃げられてしまった。 でも、いた。 確かに、いた。 今度は慎重に、慎重に、砂をゆっくりと掘った。 気付いたら、青かった空は少しダイダイ色に染まっていた。 アポロチョコレートの箱の中で20匹くらいのアリジゴクがかさこそ音を立てていた。 帰ろっか。 どちらからともなく、言った。少し放心状態だった。 歩いているうちに、辺りは薄暗くなっていった。 近くの農家に明かりが灯った。なんだか物語の中の国にいるような、不思議な感覚だった。 農道やあぜ道は真っ暗だったので、仕方なく車が走る道路わきを歩いた。歩道なんてなく、数十センチしかない白線の内側を、僕らは一列で歩いた。 ワァー!!!車のヘッドライトが通り過ぎる度に、僕らは大声を出した。 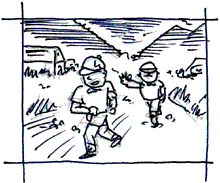 「なあ、好きな人おる?」
「なあ、好きな人おる?」神野が聞いた。 「なんでじゃ」 「わしも言うけえ、お前も教えてや」 普段なら絶対言わなかったが、今はなんだか、どうでもよかった。 「絶対言わんか」と何度も念を押してから、僕は答えた。「清水さん…」 「うそー!」と神野は叫んだ。「お前も教えーや」僕はやつの目を見ずに言った。「俺はねー…お母さん!」神野は走り出した。 「清水さーん!」叫ぶやつを、僕は追いかけた。「おらー!」 神野のうちに着いた時は、夜8時をまわっていた。神野の母親が出てきて、ただ、よかったよかった、とくり返していた。家に帰ると、母さんが怒っていた。神野の母親が電話したらしかった。父さんは、そんな遠くまで行ったのか、とあきれていた。 ***** その後しばらくして、家庭用ゲーム機が世の中を席巻する。 僕の住んでいた田舎町も例にもれずその勢いに飲み込まれ、友人達もぴたっと外に出るのを止めてしまった。 神野も学校が終わると家に直行するようになり、ゲームをしない僕とは疎遠になっていった。 僕は中学を出ると街の高校に通い、大学は東京に出た。その後は海外にまで足をのばす。 映画『スタンド・バイ・ミー』のテーマ曲を聞く度に、僕は映画の少年達に、あの時の自分を重ねてしまうのだ。 あの、ギラギラした夏の日、僕は”外に出る”ということを知ったのかもしれない。 2003.11.6. 工房の主人 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『さ〜そ』 >『スタンド・バイ・ミー』 |