|
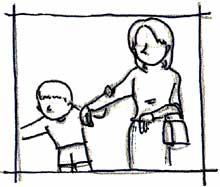 その映画を観たのは、玲子が高校に入ったばかりの頃。確か、日差しの強い夏の午後だった。 その映画を観たのは、玲子が高校に入ったばかりの頃。確か、日差しの強い夏の午後だった。
『1999年の夏休み』
21世紀を目前にした世紀末。ノストラダムスの予言が本当だとすれば、来るはずのない夏を描いた作品だった。当時15だった玲子は、遠い時間の先にある自分の未来がどうなっているのかと、ふと考えてみた。
予言が外れたとして、まだ未来が続くとしたら自分は28歳。どんな仕事をしているんだろう。結婚は?しているとしたら、例えば誰と…?
映画の不思議な空気感に翻弄されながら思っていたら、ふとバスケ部でキャプテンをやっている声の大きい男の子の顔が浮かんで来て、玲子は慌てて首を振った。
あれから14年。玲子が結婚したのは、昔あこがれた彼とは似ても似つかない温厚で物静かな夫、広樹だった。そんな相手だったからこそ、結婚して子供ができても仕事を続けることを許してくれたし、家事が多少手抜きになっても細かい文句も言わないでいてくれるのだけれど。
広樹が出張に出ていた日曜の朝、玲子は5歳になる息子の光樹を連れてファストフードの店に出かけた。誰が教えたわけでもないのに「どのセットにするとどのおもちゃが付いて来る」と、光樹はとても詳しい。アクセスやエクセルを使った計算式はすぐに理解できるのに、そんな組み合わせの計算が玲子にはできず、苦笑いするしかなかった。
スーパーに出かけても、光樹はかかとのローラーを転がして後をついて来る。冷凍食品売り場で買ったピザも、さっさとレンジに入れるし、食べ終えた皿は何も言わないうちに食器洗い機に並べてしまう。そのうち、一人遊びにも飽きたのか、ソファでうたたねを始めた光樹に毛布をかけてやりながら、玲子は目元をほころばせた。
日曜の午後、こんなにのんびりしたのは久しぶりだった。不満というわけではなかったけれど、夫と光樹に挟まれていると、一日はあっという間に過ぎてしまう。たまにはゆっくりビデオでも観ようかとラックに手を伸ばすと、学生時代に録画したビデオが何本か出て来た。この映画を観に行くか、ドライブに出かけるかで真剣に広樹とケンカしたことを思い出す。今なら、外からだって見たい番組を録画することもできるし、映画はたいていビデオになって発売される。その当時は思ってもみないことだった。
そんなビデオテープの間から、玲子はそのビデオを見つけた。映画館で観て、どうしても欲しくなってお小遣いを貯めて買ったビデオ。1999年の夏休み。
1999年。はるか先だと思っていた未来は、もうとっくに自分のうしろにある。それと同じように、その頃思っていた21世紀は、夢見ていたようなものではなかった。
車が空を飛んだり、お手伝いロボットがいたりするわけでもない。だから玲子は毎日近所のスーパーで買い物をして、夕飯の支度をしなければならないわけだし、リニアモーターカーだって実際には走っていない。だから広樹の実家のある名古屋へ里帰りするときは、昔とたいして変わらない新幹線に乗る。ジェット旅客機がマッハで飛ぶこともなければ、宇宙旅行に行けるわけでもなく、ましてや月や火星に人間が住めるようになったわけでもない。夢や憧ればかりが大きかった未来−21世紀−は、割と当たり前にやってきて、平凡な毎日へと続いていた。
確かにインターネットや携帯電話の普及は毎日を便利にした。欲しい情報は図書館などに行かなくてもすぐに手に入るようになった。けれどその反面、ゴミ問題や、高齢化社会、年金、環境破壊など、面倒で深刻な問題の方が多くなった気がするのだ。
「あなたが大きくなる頃の未来は、もっと大変かも知れないよ」
息子の髪を指に巻きつけながら、玲子は苦笑いするしかなかった。
その声が聞こえたのか、光樹が小さく寝返りを打って玲子の手を無意識に探し始める。
その瞬間、玲子は不思議な感慨に捕らわれていた。
 生まれたときは手のひらに乗ってしまいそうだったこの子が、いや、自分のお腹の中でぐるぐると動いていたものが、散歩に出た時などは自分の手をぐいぐいと引っぱって歩いて行く。その力は、ちょっと油断したらつまづいてしまいそうなほどで、現に今だって、玲子にしがみついてくる光樹の指先は、はっきりとした意志を持っている。 生まれたときは手のひらに乗ってしまいそうだったこの子が、いや、自分のお腹の中でぐるぐると動いていたものが、散歩に出た時などは自分の手をぐいぐいと引っぱって歩いて行く。その力は、ちょっと油断したらつまづいてしまいそうなほどで、現に今だって、玲子にしがみついてくる光樹の指先は、はっきりとした意志を持っている。
壮大な未来に驚かされることはなくても、ふとした驚きはこんなに身近なところにある。
自分が母親になんてなったことのほうがよっぽどの驚きだった。
「もしあの予言が当たっていたら、あなたは産まれてなかったんだよねぇ…」
自分の中から産まれて出て来たものが一人の人間として育って行くということが、少しばかり恐ろしいような気がしてつぶやいた玲子の気持ちを知ってか知らずか、傍らの小さな一人の人間は安らかな寝息をたてている。
−この子が見る未来はどんなものになるんだろう…。
予想していたものではなかったけれど、いつか見た未来は確実にここにある。そしてそれはこれからもずっと続いて行く。そしてもう自分は、未来を夢見ていた子供ではなく、この子の母親なのだ。
そう思った玲子は、手に持っていたビデオをゆっくりと棚に戻した。
2004.2.6. 水無月朋子
|
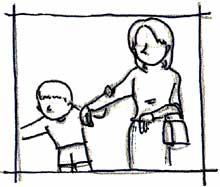 その映画を観たのは、玲子が高校に入ったばかりの頃。確か、日差しの強い夏の午後だった。
その映画を観たのは、玲子が高校に入ったばかりの頃。確か、日差しの強い夏の午後だった。 生まれたときは手のひらに乗ってしまいそうだったこの子が、いや、自分のお腹の中でぐるぐると動いていたものが、散歩に出た時などは自分の手をぐいぐいと引っぱって歩いて行く。その力は、ちょっと油断したらつまづいてしまいそうなほどで、現に今だって、玲子にしがみついてくる光樹の指先は、はっきりとした意志を持っている。
生まれたときは手のひらに乗ってしまいそうだったこの子が、いや、自分のお腹の中でぐるぐると動いていたものが、散歩に出た時などは自分の手をぐいぐいと引っぱって歩いて行く。その力は、ちょっと油断したらつまづいてしまいそうなほどで、現に今だって、玲子にしがみついてくる光樹の指先は、はっきりとした意志を持っている。