| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『か〜こ』 >『害虫』 |
|
|
| 『害虫』 |
|---|
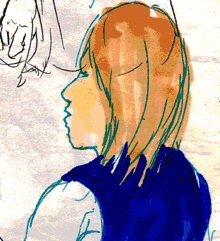 教室の中、誰かが「害虫って映画、おもしろいよ」と囁くように言った時、あの子は今日もいなかった。三年になってから私はあの子を見ていない。特に仲が良かったわけでもないが、小学校のときから同じクラスになることが多く、たまに他愛も無い話はしていた。誰かが、彼女はあなたと友達になりたがっていたみたいよ、と私に告げたことがある。
教室の中、誰かが「害虫って映画、おもしろいよ」と囁くように言った時、あの子は今日もいなかった。三年になってから私はあの子を見ていない。特に仲が良かったわけでもないが、小学校のときから同じクラスになることが多く、たまに他愛も無い話はしていた。誰かが、彼女はあなたと友達になりたがっていたみたいよ、と私に告げたことがある。その時は、何だか気味悪く感じて、友達になりたいなら直接私に言えばいいのに、と思っていた。だから彼女には仲のいい子もいなくて、いつも一人なのだ、と冷たい解釈を私はした。 彼女は決して自分を主張させたりはしない。薄い唇をひっと動かして静かに笑うだけ。黒い瞳は、虚ろに感じた。大勢の中に群れるのは苦手らしく、ふわりと遠くに離れていってしまう気がすることがよくあった。一緒にいるようで遠くに感じる、不思議な存在。 地味で目立たないあの子は何故、学校に来なくなってしまったのだろう。うちの母は、高校受験の勉強に勤しんでいるから休んでいるのよ、と大人臭い嫌な言い方をした。同じクラスの加藤さんは、男が出来たから来ないんじゃん?と生意気な中学生代表みたいな感じで言った。幼稚な男子たちは、登校拒否だ!と騒ぎ立てて笑った。先生は、大丈夫もうすぐちゃんと来るから、と曖昧な笑みを浮かべるだけである。私は、何も推測出来なかった。ただ、母や学校の皆が言っている事が外れている気はしていた。 あの子が来なくなって三週間以上が経った。私は前よりもどんどんあの子が気になりだした。窓際に埃をかぶったままひっそりと置かれている彼女の机をじっと見ていた。休み時間、他の子達がしている音楽やテレビの話にも入りたくなくなり、受験勉強もどうでも良くなっていた。それらは自分でも驚くほどに、急速に消え失せたのだ。その代わり、あの子の存在が私の中で大きく膨れあがっている。授業中、黒板上で無機質に並ぶ数字をぼんやり眺めながら、あの子は今何しているのだろうと考えていた。まるで恋でもしたかのように、私は彼女を想っていた。 笑顔が。言葉が。私の記憶の中でぼんやり佇んでいたあの子の記憶が、私の小さな脳みその中で踊っている。 それから何日か経った日、彼女を見たと言う子がいた。その日は朝から雨が音を立てて激しく降り注いでいた。教室の中は湿気で何もかもがしっとりとしていて、蛍光灯は嘘臭い光できらきらと私達を照らしていた。 多嶋さんは、肘をついてペンをいじっている私に「彼女を昨日見たんだけど」と言った。私は目をきらめかせて、どうだった?と尋ねた。勢いあまってペンを跳ね落とした私に多嶋さんは苦笑し、長い髪を指先でクルクル巻きながら語った。  多嶋さんが言うには、あの子は制服のまま一人で駅に立っていたらしい。話し掛けようとして近づいたら、面倒くさそうに笑って去ってしまったらしい。多嶋さんはその態度に何となく頭にきたと言った。そしてあの子は意味が分からなくてお化けみたいで嫌な子、と罵った。そして最後に、「なんかあの子、害虫の子みたい」と言った。
多嶋さんが言うには、あの子は制服のまま一人で駅に立っていたらしい。話し掛けようとして近づいたら、面倒くさそうに笑って去ってしまったらしい。多嶋さんはその態度に何となく頭にきたと言った。そしてあの子は意味が分からなくてお化けみたいで嫌な子、と罵った。そして最後に、「なんかあの子、害虫の子みたい」と言った。ふと前に耳に残った誰かの言葉を思い出した。「害虫って映画、おもしろいよ」という言葉。害虫?私はもの凄く気になって、立ち去ろうとする多嶋さんを呼び止めて聞いた。 「害虫?ああ、なんか社会に失望した感じの主人公の登校拒否少女がどん底まで落ちていく話、かな。」 多嶋さんはしらけた顔でそう言った。 雨音だけが響いていた。 2003.6.9. 文・画 リン |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『か〜こ』 >『害虫』 |