| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『か〜こ』 >『キャリー』 |
|
|
| 『キャリー』 |
|---|
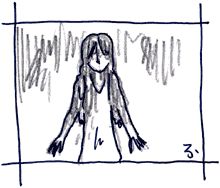 今思えば、自分は子供の頃からいじめられっ子の体質だったんだろう。昼の給湯室でお茶を淹れながら沙織はふと昔を思い出していた。今でも声をかけあってお昼に出たりするのは苦手だ。お茶も一人で淹れるし、お昼も机で食べる。そういう態度が煙たがられるのも昔も今も変わっていないらしい。
今思えば、自分は子供の頃からいじめられっ子の体質だったんだろう。昼の給湯室でお茶を淹れながら沙織はふと昔を思い出していた。今でも声をかけあってお昼に出たりするのは苦手だ。お茶も一人で淹れるし、お昼も机で食べる。そういう態度が煙たがられるのも昔も今も変わっていないらしい。ずっと学校が嫌いだった。と、いうより馴染めなかった。小さいころ体の弱かった沙織は幼稚園に行かず、だから小学校に入ってからもあまりうまく人と喋れなかった。何か言おうとすると言葉が喉で止まる。その間にも周りの話題はどんどん変わって行き、気が付くと一人で取り残されることが多かった。それでも泣きもせず、じっと黙っている沙織には暗い子だというレッテルが貼られた。 そんな頃に見た映画にキャリーというのがあった。怖い映画だよ、と言われたにも関わらず最後まで見てしまったのは、その中に出てきたキャリーという女の子が自分とすごく似ていたからだった。 ロッカールームでいじめられていたキャリーは、突然恐ろしい能力に目覚め、自分をいじめていた子たちに復讐する。沙織も「憎しみで人が殺せればいいのに」と何度思ったか知れない。けれど自分にはそんな能力はないのだ。だから沙織はキャリーを怖いとは思わず、羨ましいとさえ感じたのだった。 その頃から沙織は自分の立場というのを薄々感づき始めていた。自分の何かが他の女子の何かを刺激してしまうらしい。だから目立たないように、誰の感情も刺激しないように、教室の隅でそっと息をする。 そうしながら沙織は教室の中をじっと見つめていた。誰が誰を嫌っていて、誰が誰に媚びているか。誰が誰の気を引きたくて、誰が誰を見下しているか。狭い世界の絡まった糸を、そういう意味では沙織は誰よりも人の感情に敏感だった。 クラスで一番かわいいと言われているマユ。レースやフリルのついた女の子らしい服を着て、栗色の髪をリボンで結んでいる。マユはあどけなく振る舞いながら、その実周りの注目を集めるのが誰よりも好きな子だった。 「わぁ、マユ、新しい雑誌買ったんだー!」 「欲しいページがあったら切っていいよ。マユ、そのグループあんまり好きじゃないから」 「マユのキーホルダーかわいい!」 「よかったらあげる。マユ、もうひとつ持ってるから」 そんなふうに、休み時間のたびに教室の後ろに固まって話しているグループ。そのマユの「オトモダチ」が実はマユのことを妬みながら、そのおこぼれに預かろうとしてるのを感じた。 そして、さりげく、けれどグループの中心にいることに一生懸命なマユが、男子の前では少しばかりおっちょこちょいで、頼りない女の子を演じることも。 「…くん、今日わたし、金魚の当番なの。でも水槽一人じゃ持てないし、お水換えるの手伝ってくれない?」 やわらかそうな髪を揺らして、首を傾げてみせるマユは、きっとそうすることが自分をかわいらしく見せることを知っているのだろう。それに気づいた沙織はしらけてしまって、それ以来マユを視界から外した。そんな沙織の無関心が勘に触れたのか、マユは沙織を目の仇にし始めたのだ。 最初は無視だった。けれど沙織にしてみればそんなのは慣れっこになっている。すると今度は棘を含んだ言葉を投げつけてくるようになった。 「沙織ちゃんっていつも変わったお洋服着てるのね。それしか持ってないの?」 沙織の、何の飾りもない黒のセーターを見ながら言う。沙織は「別に…」と言ったきり相手にもしなかった。すると今度は根も葉もない噂話がクラスに流れはじめる。 「沙織ちゃんちって本当はすごく貧乏なんだって。だからマユは優しくしてあげようと思ってるのに…」 マユの優しさが判らない沙織は意地悪でひがみっぽくて暗い子。次から次へとそんなイメージが重ねられる。 マユの苛立ちを感じならも、沙織はそれすらも相手にしなかった。 ある日、沙織が体育を見学した日の帰り。HRの時間になって、「ママに買ってもらったブランドのポーチがない!」とマユが騒ぎ出した。グループの誰かがすかさず手を上げて言う。 「今日の体育見学したの、沙織ちゃんだけだったよねぇ…?」 きっとその時に盗んだんだろうと言いたいのがあからさまだった。だって沙織ちゃんのおうちは貧乏だから。きっとそうよ。他にそんなことする人なんていないもん。ねぇ? 身に覚えのないことを弁解する気にもならず、机の中に手を突っ込んだ沙織は愕然とした。そっと手元に引き寄せてみる。なくなったはずのマユのポーチがそこにあった。 「…先生!」 沙織は思い切って言ってみた。 「浦野さんのポーチ、ここにありました。でも私が盗ったわけじゃありません。もし私が盗ったとしたら、自分で盗んで、みんなの前でわざわざ返すのも変だと思います」 やってみれば簡単なことだった。凛とした様子で立ち上がり、理路整然と話をする沙織に反論することなど誰もできなかったのだ。そしてその場はマユの不注意ということで収まった。けれど悔しそうにうつむくマユの横顔を沙織は見逃さなかった。 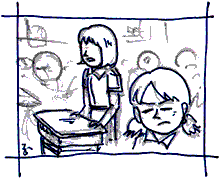 その日の帰り道、一人で歩いていた沙織の後を追いかけて来た子がいた。同じクラスの男子だった。
その日の帰り道、一人で歩いていた沙織の後を追いかけて来た子がいた。同じクラスの男子だった。彼は照れくさそうに向き合いながら、あのさ…と切り出した。 「俺さ、工藤ってすげえと思う。浦野のことかわいいって言うやついっぱいいるけど、俺は工藤の方がすげえと思う」 「……そう」 「ほら、そういうとこ。普通のやつだったら大騒ぎするのにさ、おまえ何にも言わねえもん。大人っぽいっていうかさ、何かよく判んねえけどすげえよ、おまえ」 それまで「暗い」としか形容されなかった沙織の雰囲気を「落ち着き」という別のものだと理解した初めての子だった。彼が何を言おうとしていたのか、今なら判る。きっと彼は周りの子たちより少しだけ早く大人になり始めていたのだろう。その時は、そんな自分の変化さえ沙織自身も気がついてはいなかったけれど。 それは沙織が中学に入る少し前の、冬の日のことだった。 2003.8.12. 水無月朋子 |
|
映画工房カルフのように
【http://www.karufu.org/】
All rights reserved ©2001.5.5 Shuichi Orikawa as_karufu@hotmail.com |
| ホーム> 映画にまつわるものがたり> 『か〜こ』 >『キャリー』 |